2005-07-09[n年前へ]
■ファイト 
西原理恵子が描くNHK連続ドラマ「ファイト」のエンディング・ギャラリーを眺める。「まえをみる ひとつだけすすむ。」の言葉と、その中に描かれた人の表情が一番のお気に入り。

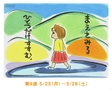


2007-04-20[n年前へ]
■Mannequin Head Maker 



けれど、組み立てた坊主頭のマネキン・ヘッドは、その段階では、まだ素材に過ぎません。太い油性マジックを手にとって、あるいはカラフルなクレヨンを握り、好きな髪型でも描いてみましょう。あるいは、赤いクレヨンを口紅に見立てて唇を赤く彩ってみるのも面白いことでしょう。はたまた、薄い色鉛筆で頬に彩りを添えてみたり、眉を整えてみるのも良いかもしれません。組み立てたマネキン・ヘッドをキャンバスにして、あなたが好きな化粧や髪型を作り出して描いてみるのが、それがMannequin Head Maker の楽しみ方です。立体的に顔が描かれたキャンパスに、筆を走らせてみることができるのが Mannequin Head Maker の味わい方の1つです。好きな髪型や化粧の下書き・あるいは苦手な髪型の実験台として、本当の人の代わりにマネキン・ヘッドを使ってみるのも、きっと面白いと思います。


紙でできたマネキン・ヘッドを横に向ければ、その顔はあなたに横顔を見せることでしょう。その顔を下に向ければの口や目の配置から、少し「笑顔」を見せるはずです。そして、マネキン・ヘッドを少し上に向ければ、その顔はちょっと怒った顔を見せるだろうと思います。あるいは、斜め下から眺めれば、なぜか憂いを帯びた顔を見せ、斜め上から眺めれば含み笑いを浮かべている…。そんな具合に、マネキンヘッドの表情がカラフルに変化するように、顔の部品が正二十面体上の適切な位置(変上)に配置されています。それがMannequin Head Makerです。
つまり、Mannequin Head Maker は、好きな顔を掌の上に作り出し、あなたの思い通りの装いをさせることができ、そして、あなたの好きな表情を作り出すことができるWEBサービスです。平面的な写真から、立体的な表情や姿を作り出すことができるちょっとおかしなWEBサービスです。
Icosahedron Worlds と同じように、処理された展開図は、ブラウザ上では一見小さな画像に見えます。しかし、実際には非常に大きなサイズの画像ファイルです。また、その他の使い方自体も、Icosahedron Worldsと同じになっています。組み立てる時には、のりでなく両面テープを使った方が楽でしょう。
2007-07-07[n年前へ]
■市場経済と万有引力と「神の見えざる手」 
『国富論』を書き、"経済学の父"と称されるアダム・スミスはアイザック・ニュートン(1642-1727)に強い影響を受けたという。
18世紀に経済学の基礎を作ったアダム・スミスが、非常に強い影響を受けたのは、ニュートン的な“科学”です。 栗田啓子 万有引力と神の見えざる手アダム・スミス(1723-1790)が生きていた時代、多くの人たちが、世界・社会を動かす基本的な法則性や自然科学の法則性に、神の意思が表れていると考えていた。万物に、普遍的な(けれど見えない)“万有引力”が働いているとニュートンが考えたのと同じように、アダム・スミスが経済発展の歴史や市場均衡の陰に「神の見えざる手」が動いていると考えた…というのは不思議に、そしてとても面白い。
経済学と古典物理学という、まるで分野が離れて見えるようなことなのに、実は同じ時代の中で影響を受けあいながら共に育ってきた…ということを意識するならば、その2つが不思議なくらいピタリと綺麗に重なり合う。それは意外でもあるけれど、同時に、それも当然なことであるようにも感じる。
アダム・スミスが考えた「経済人=ホモ・エコノミクス」という存在がどうしても納得できませんでした。自分の利益にのみ従って、完全に合理的な行動をする人間。自分の進むべき方向を確実に知ることができて、必ずその方向へ動く。そんな顔も表情もない人間なんて現実にいるわけがないし、そんな非現実的なモデルに何の意味があるのだろうか?と思うこともあったのです。 (けれど、ニュートン力学で物体を示す質点だって)大きさもなければ、色もついていない、そんな存在です。ニュートン力学は、物体をそんな奇妙な存在として扱うにもかかわらず、数多くの用途で必要十分な精度の計算・予測をすることができます。 柴田 研 ニュートンと経済人世の中に、「100% 新しい考え・アイデア」なんてほとんどない。いや、多分、そんなものはない。そんなものがある、という人がいたとしたら、単に歴史を振り返ったことがない人だろう。
逆に言えば、どんなこと・どんなものであったとしても、必ず古い家系図のように、考えやアイデアの歴史を辿ることができるに違いない。どんなことでも、少しづつ考えが変化し、ほんの少しづつ新しいものが生まれ、少しづつ前へ進んでいく。意識的に、あるいは無意識的に、異なるように見える色んなものが少しづつ影響を受けあってきた。そんなさまを知ることは、とても楽しい。
2008-01-24[n年前へ]
2008-09-28[n年前へ]
■アンディ・ウォーホルと"inter view" 
"double meaning"で、その二つの"meaning"が相反すること、にいつも見とれる。二つの重なる言葉、けれど、それらがまるで反対のことを意味する言葉が好きだ。なぜなら、それが現実だから、だと思っている。もしも、片面しか見せないものがあるとしたら、(このフレーズは何度も書いているが)映画のセットのように薄っぺらいものでしかない、と思っている。"inside out"なんていう言葉が好きな理由は、そんな気持ちからだ。
アンディ・ウォーホル・ミュージアムで、ウォーホルが創刊した「インタビュー(interview)」誌が壁の一面に並んでいた。多くの観客は、表紙に描かれたインタビューイの表情を眺め、それが誰かを確かめる。そして、傍らにある本棚からそのインタビューイが語った言葉を眺めている。
その雑誌「interview」というタイトル・ロゴは、デザインのせいか、どれもすべて"inter View"という風に見えた。「内面を覗いたもの」というタイトルの雑誌と、アンディ・ウォーホルの「僕を知りたければ作品の表面だけを見ればいい。裏側には何もない」という言葉、そのまるで反対の言葉、"double meaning"な言葉がとてもいい。
「表面だけを見ればいい。裏側には何もない」という言葉は、その「裏側の実在・裏側に惹かれる心」があってこそ、の言葉だと思う。「表面だけ」で「後ろに何もなかったとしたら」、それは後ろに倒れてしまう。・・・だから、と書き続けるには論理的に飛躍があるけれど、「表面だけを見ればいい。裏側には何もない」という言葉が意味を持つためには「裏側の実在・裏側に惹かれる心」という方向性がなくてはならない。つまり、これは一種のパラドクスな言葉である。それが、実に的確だ、と思う。
