2010-02-01[n年前へ]
■「しゃべり過ぎの時代」と「いしぶみ」 
 映画「おくりびと [DVD]
映画「おくりびと [DVD]
」のモチーフにも使われた、向田邦子の「男どき女どき
」に収録されている「無口な手紙」から。
現代は、しゃべり過ぎの時代である。
昔、人がまだ文字を知らなかったころ、遠くにいる恋人へ気持ちを伝えるのに石を使った、と聞いたことがある。男は、自分の気持ちにピッタリの石を探して旅人にことづける。受け取った女は、目を閉じて掌に石を包み込む。
2010-02-02[n年前へ]
■「深い後悔」や「苦い失敗」 
 本当に引用したい一文は、自分の手帳に書き写すだけ、ということが多いものです。
本当に引用したい一文は、自分の手帳に書き写すだけ、ということが多いものです。
小山薫堂は、映画「おくりびと
」の脚本を書いた人です(それ以外のことも数えきれないくらいしている方ですが)。その「おくりびと」に関する一節を、小山薫堂の「もったいない主義―不景気だからアイデアが湧いてくる! (幻冬舎新書)
」から、1番ではないけれど、気になった言葉をここに書き写しておくことにします。
ある映画評論家の人からはこう言われました。「あの脚本は誰が撮っても面白くなったに違いないけれど、監督が滝田洋二朗だからこそ、さらに輝きを増した」
滝田監督はピンク映画の出身です。だから、職業差別を受けた経験がある。そのコンプレックスが、この映画に反映されているのではないか。(中略)差別される側の痛みを、滝田監督は実感としてよく理解していたのかもしれません。
最初に僕が石文というものの存在を知ったのは、向田邦子さんの「無口な手紙」というエッセイを読んだときでした。
2010-02-03[n年前へ]
■孤独に効く(安易な解決という見方もある)「○×△□」というもの 
 広告批評 編「私の広告術
広告批評 編「私の広告術
」の岡康道の言葉から。
”孤独”って、人間の一番嫌なことだと思うんです。それが嫌だから、それに耐えるために、いろんなものが用意されているんじゃないか、とさえ思ってる。
で、「○×△□」というのは、孤独に一番効くものだと思います。それが安易な解決だとか、そういう批判はあるかもしれないけれど。
この「○×△□」の部分には、あるメディアが入る。この「○×△□」はきっと、時代・場所によって違うことだろう。ただし、その部分さえ入れ替えれば、この引用文はいつの時代にも通用する言葉であるのかもしれない。
2010-02-04[n年前へ]
■本当にいいものは太陽の方を向く 
 北村薫の「朝霧
北村薫の「朝霧
」
本当にいいものはね、やはり太陽の方を向いているんだと思うよ。
4歳くらいの頃、長野県の野辺山という高原に越した。太陽が空に昇っている時刻には、いつも太陽の方向を向いている巨大なパラボラアンテナ=朱色の電波望遠鏡が、その高原には何基も立っていた(参考:宇宙経由 野辺山の旅
)。向日葵(ひまわり)のように、それら、離れた所に立っているいくつもの巨大なパラボラアンテナたちは、いつも太陽の方を向いていた。そんな風景の中で暮らしていた頃を思い出す。

2010-02-05[n年前へ]
■「はるか」のアンテナ 
 平林久・黒谷明美「星と生き物たちの宇宙―電波天文学/宇宙生物学の世界 (集英社新書)
平林久・黒谷明美「星と生き物たちの宇宙―電波天文学/宇宙生物学の世界 (集英社新書)
」から。
「はるか」の最も重要な大きなアンテナの展開はどうだったのでしょう?そもそも、アンテナはどういう仕組みで展開するようになっていたのですか?
この方式を進めたのが、当時宇宙科学研究所で「はるか」アンテナ開発主任だった三浦公亮先生です。折り紙の権威で三浦折りの発明者です。
「はるか」のアンテナは三浦折りだと勘違いされることが多いのですが、全く違う概念です。
著者の片方(私の父)は、何十年来、hiraxという名前を使い・そう呼ばれている。それが、hirax.netの"hirax"の由来である。
2010-02-06[n年前へ]
■「二者択一の積み重ね」 
 「忘れられない、あのひと言
「忘れられない、あのひと言
」に収録されている、映画監督である張芸謀の言葉、そしてそれを受けての阿川佐和子の文章。
(そして監督は静かにおっしゃった)「でもね、人生なんて、そんなものじゃないかと思うんです。私のように理想なんか持たず、運命に翻弄(ほんろう)されて、いたしかたない選択を繰り返していても、いつのまにか道が開けているんですから」
目の前に突き付けられた二者択一を、その場の理由で選び続ける。それがたとえ本意でなくとも、選んでいるのは自分である。そしてその選択の積み重ねがどれほど予想外の方向へ行っていたとしても、自分が選んだ道なのである。
2010-02-07[n年前へ]
■「書くことだけがお前を助ける」 
 「忘れられない、あのひと言
「忘れられない、あのひと言
」に収録されている、船曳建夫の文章から。
そんな頃、その日も思うように書けず、昼飯時にとぼとぼ歩いていると、反対側の歩道を行くフォーティス先生を見かけた。先生はこちらを認めると、突然、道を横切り、私の前に来た。そして、日本語に直訳すると、「書くことだけがお前を助ける」と私に言い渡し、去って行った。この一言は私に響いた。
この言葉は博士論文を書いている若者だけではなく、多くの人に励ましの言葉となると考え、ここに再び載せる。
2010-02-08[n年前へ]
■「デーモン」(魔人)という、人間を創造的活動に駆り立てる根源的な焦燥 
小山慶太「科学者はなぜ一番のりをめざすか―情熱、栄誉、失意の人間ドラマ (ブルーバックス)
」から。
ドイツの作家シュテファン・ツヴァイクは、人間を創造的活動に駆り立てる根源的な焦燥(しょうそう)を「デーモン」(魔人)と呼んだが、その言葉を借りれば、彼らはまさにデーモンにとりつかれた人間ということになるのかもしれない。そして、片時も立ち止まることなく、まるで立ち止まることが恐怖であるかのように論文を発表し続ける衝動もまた、先取権獲得にかける執念の強いあらわれなのであろう。
2010-02-09[n年前へ]
■「恋愛旅人」と「頁の折り目」 
 角田光代 「恋するように旅をして
角田光代 「恋するように旅をして
」(旧題「恋愛旅人」)から。
小学校の高学年が一、二年で学ぶことを、二十歳をすぎた私は十年以上かけて学びつつある。アジアとヨーロッパの区別。大陸の区別。そこで生産される製品と、そこで生きる人々。人々の持つ歴史と、彼らの食べる日常食。差別ということ。和解ということ。
古本で「恋するように旅をして
」を買い、列車の中で頁をめくる。読み進めていると、端に折り目のある頁が、いくつかあった。
 私の前にこの本を読んで、頁の端を折った誰かは、一体どの言葉に惹かれたのだろう。頁の端っこをどちらの面に向けて折り、そして、どの言葉を記憶しておこうと思ったのだろうか。
私の前にこの本を読んで、頁の端を折った誰かは、一体どの言葉に惹かれたのだろう。頁の端っこをどちらの面に向けて折り、そして、どの言葉を記憶しておこうと思ったのだろうか。
本を読みながら誰かが感じたことの痕跡が、頁を折った跡の向こうに見える。その人の感じた道のりを、ふと辿ってみたくなる。その気持ち・心の動きは、少し、恋愛に似ている。
2010-02-10[n年前へ]
■何の意味もなく、誰にでも可能だけれど、酔狂な奴でなくてはしそうにないことを… 
 沢木耕太郎「深夜特急〈1〉香港・マカオ
沢木耕太郎「深夜特急〈1〉香港・マカオ
」から。
ほんのちょっぴり本音を吐けば、人のためにもならず、学問の進歩に役立つわけでもなく、真実をきわめることもなく、記録を作るためのものでもなく、血涌(わ)き肉躍(おど)る冒険活劇でもなく、まるで何の意味もなく、誰にでも可能で、しかし、およそ酔狂な奴(やつ)でなくてはしそうにないことを、やりたかったのだ。
インドのデリーからイギリスのロンドンを目指し、2万キロメートルを超える道のりを、一年以上の時間をかけ乗合いバスに乗って行く。その旅は、確かに酔狂な奴でなくてはしそうにない。だからこそ、その旅を小説を通して追体験することができるのは、とても楽しい。
2010-02-11[n年前へ]
■「星の王子さま」を捧げられた人 
 サン・テグジュペリ「星の王子さま
サン・テグジュペリ「星の王子さま
」冒頭の献辞から。
レオン・ウォルトに
わたしは、この本を、あるおとなの人にささげたが、子どもたちには、すまないと思う。(中略)そのおとなの人は、いまフランスに住んでいて、ひもじい思いや、寒い思いをしている人だからである。どうしてもなぐさめなければならない人だからである。
 サン・テグジュペリ「ある人質への手紙―戦時の記録〈2〉 (サン=テグジュペリ・コレクション)
サン・テグジュペリ「ある人質への手紙―戦時の記録〈2〉 (サン=テグジュペリ・コレクション)
」から。
今夜しきりに思い出す人物は今五十歳だ。彼は病気だ。それにユダヤ人だ。どうして彼にドイツの恐怖を乗り越えられよう?
2010-02-12[n年前へ]
■「場所と人の関係」は「恋愛の関係」に似ている 
 角田光代 「恋するように旅をして
角田光代 「恋するように旅をして
」(旧題「恋愛旅人」)の「ポケットに牡蠣の殻」から。
場所と人の関係というのは、恋愛にひどくよく似ていると思う時がある。この文が書かれるまでの流れ、そしてこの文が唐突に始まる、その流れが小気味よい。文章の一節ごとの繋がりが、そして、それら文章の一節ごとの跳ね具合が、まるでコブ斜面を蝶のように舞うスキーヤ―を見ているような心地になる。
場所と人の関係が本当の恋愛と決定的に違うことがたったひとつだけある。前の一節、次の一節・・・前のコブ、次のコブ・・・力を抜いて跳んで、体を固めて次へ飛ぶ。そんな動きを眺めているような気持ちになる。
2010-02-13[n年前へ]
■下手な俳優は台詞を言うのと同時に指を指す。 
 アニメーターであり、『ロジャー・ラビット(Who Framed Roger Rabbit)』のアニメーション監督であるリチャード ウィリアムズによる「アニメーターズ・サバイバルキット
アニメーターであり、『ロジャー・ラビット(Who Framed Roger Rabbit)』のアニメーション監督であるリチャード ウィリアムズによる「アニメーターズ・サバイバルキット
」から。
下手な俳優は、セリフを言うのと同時に指を指す。この言葉が意味しているのは、(動きが非常に遅い場合を除いて)観客は「同時に起こるいくつものこと」を見てくれない。だから、「わかりやすく」伝えるためには、「まず指を指してから、(たとえば)『あいつは向こうに行ったよ!』と言う」とか、その逆に「『あいつは向こうへ行った!』と言ってから、指差す」といったようにした方が良い、ということ。
このような「伝達」をするための基本的なテクニックは、「人というもの自体を知る」ということにも繋がり、とてもためになる。
2010-02-14[n年前へ]
■夢を持てと気楽に語る人の残酷さ 
 森永卓郎 「新版 年収300万円時代を生き抜く経済学 (知恵の森文庫)
森永卓郎 「新版 年収300万円時代を生き抜く経済学 (知恵の森文庫)
」巻末に掲載されている玄田有史による「解説」から。
勝ち組はよく、人生に必要なのは夢だ、と語る。しかし、夢を持てと気楽に語る人の残酷さを、私は好きになれない。
2010-02-15[n年前へ]
■忘れられない瞬間は突然やってくる。 
 「青春18切符のポスター」から。(関連:旅少女)
「青春18切符のポスター」から。(関連:旅少女)
旅は、予想できない。忘れられない瞬間は突然やってくる。列車に揺られ、ホームで待ち、改札口を抜けて歩き出す。その繰り返しのどこかで、何かが待っているんだ。
「線路(レール)の先の物語」
1991年 夏 青春18切符
レール、レイル、線路…色々な言い方がありますが、あなたの線路の先にあるもの、レールのさらに先にあるものは、一体何ですか?

「決められたレール」は無いほうがいい。現在、この文章を書いている hirax.netは、主として"Rails"というフレームワークを利用しています。それは、また一方で、人が「決められたレール」を好むということを示しているようで、一筋縄ではいかない確かな真実を現わしているような気がします。ふと、そんな複雑な思いに襲われます。
「何かを変える旅。」
1995年 冬 青春18切符
2010-02-16[n年前へ]
■近くても 遠くても、見えないね。 
 南流石が率いる流石組の踊りも気持ち良い、PSY・S(サイズ)の「FRIENDS OR LOVERS」から。(Wondering up and down もとても良い)
南流石が率いる流石組の踊りも気持ち良い、PSY・S(サイズ)の「FRIENDS OR LOVERS」から。(Wondering up and down もとても良い)
近くても 遠くても、見えないね。
声届くかな?
ねぇもっと、リラックスして。
ほら、風が吹いてる。
ドア開けて、ためらわず、行ったり来たりしようよ。
2010-02-17[n年前へ]
■諺(ことわざ)・名言が響かす心地よいリズム 
 諺(ことわざ)・名言には心地良いリズムがあり、そして、何度繰り返し聞いてみても辿りつくことのできない奥深さがある。
諺(ことわざ)・名言には心地良いリズムがあり、そして、何度繰り返し聞いてみても辿りつくことのできない奥深さがある。
Easy to say, hard to do. Saying and doint are two things.金言とそ実例が繰り返されるような、そんな文の連なりを読んでいると、魅力ある山道を歩き・景色を眺めているような気分になる。
言うは易く、行うは難し。「案じるより団子汁」「好きこそ物(もの)の上手なれ」「古きを温(たず)ねて、新しきを知る」…七五のリズムが心地良く体と頭の中に強く響いてくる。
 規則正しく、しかし同時に緩急も備えた文章は、究極かつ至高のショートショート集なのかもしれない。
規則正しく、しかし同時に緩急も備えた文章は、究極かつ至高のショートショート集なのかもしれない。
(ギリシア哲学のターレスに、ある青年が聞いた)「では、いちばん易しいことは?」彼は片目をつぶってニヤリ一言。「他人に忠告することだよ」
2010-02-18[n年前へ]
■愚者は教えたがり、賢者は学びたがる。 
 「スプレッドシートを使ったシミュレーション入門」という講習会を、何回か手伝っている。その講習会が開催されて何回目かのとき、離散粒子法(DEM)の第一人者といっても良い研究者が、その講習会に参加申し込みをしてきて、実際、エクセルを使っていたって真面目に計算作業をしていた。
「スプレッドシートを使ったシミュレーション入門」という講習会を、何回か手伝っている。その講習会が開催されて何回目かのとき、離散粒子法(DEM)の第一人者といっても良い研究者が、その講習会に参加申し込みをしてきて、実際、エクセルを使っていたって真面目に計算作業をしていた。
愚者は教えたがり、賢者は学びたがる。上の言葉はもしかしたら、こう言い換えても良いのかもしれない。
チェーホフ
学びたがる人は賢者であることが多く、教えたがる人は愚者であることが多い。もっとも、賢者と愚者のどちらが、何か為す人であるか否か、ということは、また別である。
2010-02-19[n年前へ]
■「分かれること」「繋がること」への欲求 
 人には「分ける」「差異を見出す」ということへの欲求があるのだろうか。そんな分類・区別・差別化することへの欲求が人の底にはあるのではないか、と強く感じてしまうくらいに、理系と文系・科学と非科学・人文科学と自然科学・科学者と技術者…そんな話は何百年も前から、無限ループのように繰り返し続けられている。
人には「分ける」「差異を見出す」ということへの欲求があるのだろうか。そんな分類・区別・差別化することへの欲求が人の底にはあるのではないか、と強く感じてしまうくらいに、理系と文系・科学と非科学・人文科学と自然科学・科学者と技術者…そんな話は何百年も前から、無限ループのように繰り返し続けられている。
ひとつのものには、そのひとつのものの中に、色んな側面がある。たとえば、科学は、応用を通じて実生活に関わる面もあれば、知的追求という点からこころの喜びにも関わる面も持っている(この一節はリンク先の本の「あとがき」にある言葉である)。何かを分けようとするとき、それはあくまでひとつの側面を描こうとしているに過ぎない。
しかし、悪い人間という一種の人間が世の中にあると君は思っているんですか?そんな 鋳型に入れたような悪人は世の中にあるはずがありませんよ。
夏目漱石 「心」
 「ひとつのものには複数の側面がある」という言い方も、それもまた「分ける」ということへの欲求と表裏一体でもある。「分ける」ということは、「重ねる」ということと真逆なようで、実はよく似ている。
「ひとつのものには複数の側面がある」という言い方も、それもまた「分ける」ということへの欲求と表裏一体でもある。「分ける」ということは、「重ねる」ということと真逆なようで、実はよく似ている。
「分ける」という言葉の裏に寄り添う「統一する」ということへの欲求に、「ひとつのものには複数の側面がある」という言葉は繋がるのかもしれない。そんな、「分ける」「繋げる」ということの繰り返しで、私たちの世界観は進んできたのではないだろうか。
その主語・目的語を、明示的に私自身とした時には、それは「分かれること」「繋がること」への欲求ということになる。そう考えてみても、その繰り返しで私たちの世界は時を進めてきたのかもしれない、とふと思う。
2010-02-20[n年前へ]
■「青春18きっぷ」で「日本の隅っこ」への小さな旅をする 
BGM音楽も素敵だったデジタローグ版「旅少女
」から。
このCD-ROMに収められた写真は、JRグループの「青春18きっぷ」のポスターのために3年間にわたって撮影されたものです。その3年間、年に3解、アラキ(荒木経惟)さんと、私たち数名のスタッフは、日本の隅っこの方を選ぶようにして3・4日の小さな旅を楽しんでは、たくさん写真を撮って帰ってきていました。
佐藤澄子

2010-02-21[n年前へ]
■賢明になるほど、腰低く他人から学ぶ 
 過去を、そして遥か未来を見通した、イギリスの哲学者ロジャー・ベーコンの言葉から。”ベーコンは当時としては先駆的な思想であったが、研究者たちに聖書の原典の言葉、ギリシア語、ヘブライ語を学ぶことを求めた。”
過去を、そして遥か未来を見通した、イギリスの哲学者ロジャー・ベーコンの言葉から。”ベーコンは当時としては先駆的な思想であったが、研究者たちに聖書の原典の言葉、ギリシア語、ヘブライ語を学ぶことを求めた。”
人々が賢明になればなるほど、ますます、彼らは腰を低くして、他人から学ぼうとする。
ロジャー・ベーコン (Roger Bacon)
2010-02-22[n年前へ]
■文章の目的と、その手段・方法について 
「 文章というものについて知りたいのであれば、この一冊を読むべしという、丸谷才一の「文章読本 (中公文庫)
文章というものについて知りたいのであれば、この一冊を読むべしという、丸谷才一の「文章読本 (中公文庫)
」中で書かれている文章から。
文章というものは、判断や意見を相手に伝え(伝達)、あわよくばそれを信じさせるために書かれる。
 「論理的」ということでなく、人への「伝達」、人との「コミュニケーション」ということを(プレゼン資料を添削する作業を繰り返すことを通して)考えて、そして気付いたことを書いた「論理的にプレゼンする技術 聴き手の記憶に残る話し方の極意 (サイエンス・アイ新書)
「論理的」ということでなく、人への「伝達」、人との「コミュニケーション」ということを(プレゼン資料を添削する作業を繰り返すことを通して)考えて、そして気付いたことを書いた「論理的にプレゼンする技術 聴き手の記憶に残る話し方の極意 (サイエンス・アイ新書)」の3刷目が近々出ます。
「基本ができる」ことは「応用することもできる」という言葉、基本ができれば何でもできる、逆にいえば基本ができる人は実は少ないという言葉を眺めたとき、そんな内容に納得することも・違和感を持つこともあるかもしれません。そのどちらにしても、少しばかりの時間を費やし、ご一読して頂ければ幸いです。
2010-02-23[n年前へ]
■南海泡沫事件で1億円失ったアイザック・ニュートンの名言 
 三井住友銀行コンサルティング事業部 編集・高橋 進「スローライフのマネー学―ゆっくり生きよう、しっかり殖やそう
三井住友銀行コンサルティング事業部 編集・高橋 進「スローライフのマネー学―ゆっくり生きよう、しっかり殖やそう
」から。
「バブル」の語源となった「南海泡沫(サウスシー・バブル)事件」は、1720年の英国で発生しました。
…万有引力の法則を発見した天才ニュートンは、当時の株価バブルに踊って、大枚2万ポンド(現在の1億円に相当)を失っているのです。

ニュートンは、暴落以前に一度は投資から手を引いたのですが、バブルに踊る大衆の熱気にあおられて、再度買いに走って大失敗。
「私は物体の運動は測定できるが、人間の愚行を測定することはできない」という名文句を後世に残しました。
「南海泡沫(サウスシー・バブル)事件」とニュートン・ラグランジェといった科学者がいた時代背景を一目で確認してみたい人は、「理系サラリーマン 専門家11人に「経済学」を聞く! (Kobunsha Paperbacks Business 17)
」の巻末1を見ると良いかもしれません。
2010-02-24[n年前へ]
■評論・エッセイが届くのは「賢い人」(だけ)ではないのか? 
 鴻上尚史の「ドン・キホーテのピアス」No.658 「物語という手段でしか届かないもの」から。
鴻上尚史の「ドン・キホーテのピアス」No.658 「物語という手段でしか届かないもの」から。
たぶん、評論やエッセイで届けることができるのは、じつは、「賢い人」なんじゃないかと思っているのです。
もっとガンコでもっと臆病でもっと弱くてもっと真剣でもっと壊れやすい人に届けるためには、物語という手段をちゃんと考えないといけないんじゃないか、と思いだしているのです。
この記事原文では、「賢い人」には括弧がついていません。つまり、賢い人と書かれています。しかし、あえて、上の文章では括弧を付けました。
そう改変した理由は、そうした方がより現実に近く・より普遍性を持つのではないだろうか、と私はそのように思うからです。そう思うので、括弧(カッコ)を上記文章に付加してみました。
2010-02-25[n年前へ]
2010-02-26[n年前へ]
■統計はビキニ水着のごとく実は肝心な部分を隠す 
 阿刀田 高「殺し文句の研究 (新潮文庫)
阿刀田 高「殺し文句の研究 (新潮文庫)
」から。
統計はビキニ型の水着と同じである。さらけ出しているように見えるが、肝心要(かんじんかなめ)のところは、隠されている。
ウィンストン・チャーチル
2010-02-27[n年前へ]
■他人に何かをする、ということ 
 後藤繁雄「彼女たちは小説を書く
後藤繁雄「彼女たちは小説を書く
」中、赤坂真理の言葉から。
他人に何かをしたいっていうのは、あんまり、思っちゃいけないことと思うけど。コントロール願望に繋(つな)がりかねないから。
 鴻上尚史「ロンドン・デイズ
鴻上尚史「ロンドン・デイズ
」から。
古今東西の権力者が語る権力の最高の会館は、人間を操縦することである。お金でも色でも美食でもなく、人間を操縦すること。
 中井英夫「新装版 虚無への供物(上) (講談社文庫)
中井英夫「新装版 虚無への供物(上) (講談社文庫)
」「新装版 虚無への供物(下) (講談社文庫)
」から。
「人間を実験材料にして、好きなように操る興味が、一度もわかなかったといい切れるかどうか。本当の意味で一番残酷だったのは誰(なの)か、どうしても知りたいの」
2010-02-28[n年前へ]
■「嘘」と「外面」という「阿吽像」 
 中町綾子「ニッポンのテレビドラマ 21の名セリフ
中町綾子「ニッポンのテレビドラマ 21の名セリフ
」の、向田邦子脚本に関する「じょうずな嘘」の項から。
「生まれてはじめて嘘をつきました。一番大事なことは、人に言わないということが判りました。言わない方が、甘く、甘酸っぱく素敵なことが判りました。
「あ・うん」 第四回 さと子の台詞から
向田邦子は嘘を描いた人である。向田邦子を愛する人は、その嘘を嘘と知りつつ好んでいるような気がする。それは、たとえば、久世光彦である。
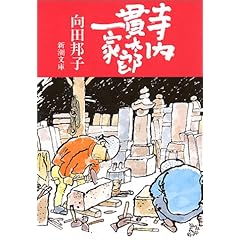
小説版「寺内貫太郎一家」の解説で、演出の久世光彦は向田邦子のことを嘘のうまい人と言っている。そういう向田邦子の嘘を感じつつ、憧れる人の気持ちは、わかるように思う。あるいは、久世光彦が書く言葉なら、それは、とても頷けるような気がする。嘘を感じた上で、それに頷きつつ、憧れる人の気持ちなら、わかるような気がする。
「嘘を上手につく人でした。実際にあったことを人に伝えるとき、いやな部分は捨て不愉快な台詞は愛嬌のあるものに書き直し、舞台装置や衣装も心楽しいものに作り変えて話すことを嘘つきというのなら、向田さんは大変な嘘つきでした。一日の大半は嘘をついて暮らしていました。夢のある嘘をついて、心痛むことの多い人生を楽しくしようとしていました」
「笑(わら)いばなし」にゃ、できないのかい。向田邦子の「入口」は「嘘」と「外面」である。その二つの阿吽像を過ぎた先こそが、向田邦子の魅力だと思う。
「寺内貫太郎一家」 祖母きんの台詞から。

